熊川宿 特徴

熊川の町並みの特徴は、街道に面して多様な形式の建物が建ち並んでいるところです。
すなわち、町屋の間に土蔵が建っていたり、町屋も「平入(ひらいり)」と「妻入(つまいり)」の建物が混在したり、「真壁造(しんかべづくり)」と「塗込造(ぬりごめづくり)」の建物が混在していることです。
このように、全く形式の異なる建物が混在しながらも、連続性をもった町並みを形成していることが、熊川の町並みの特徴です。
熊川は国の重要伝統的建造物群保存地区です。
前川(用水路)

熊川宿の歴史的景観に欠かせないのが、豊富で流れの速い水路としての前川にあります。上ノ町の前川は、大杉の更に上流の北川と天増川(あますがわ)の合流地点で取水されたもので、街道に沿って流れながら、中条橋のたもとで河内川に落ちます。中ノ町の前川は、河内川の水を取り入れて、下ノ町へと流れていきます。家ごとに、「かわと」と呼ばれる水利施設が設けられています。
町並みの特徴
平入建物とは、棟を街道に対して平行させた建物のことで、街道側では軒が真直ぐに見えます。 妻入建物とは棟を街道に対して直角に置く建物のことで、街道側では、屋根の三角の部分が見えます。 真壁造とは柱を見せる形式のことで、塗込造とは柱や軒などの木の部分を壁で隠してしまう形式のことです。

【真壁造】

【塗込造】
町屋の外観
町屋の古いものは、二階の低い「厨子(つし)二階」で、新しいものは二階の高い「本二階」です。二階を本二階として一階と同じように使用するのは新しい傾向です。
「厨子二階」の正面には、格子の付いた窓があり「虫籠窓(むしこまど)」と呼ばれています。
屋根の上面がわずかに凸となる「起り(むくり)」をもち、瓦は光沢のない若狭産のいぶし瓦が葺かれ、雪止瓦も使われています。
また、煙抜きのための「越屋根(こしやね)も、所々で見られます。
問屋であった家の正面入り口の柱には、馬をつなぐ「駒(こま)つなぎ」という鉄の輪が今も残っているところがあります。
さらに、隣家からの延焼を防ぐために「袖壁卯建(そでかべうだつ)」を持った建物もあります。

【厨子二階】

【本二階】

【虫籠窓】

【駒つなぎ】

【蔵と平入と妻入の家並み】

【袖壁卯建】

【起り・越屋根】

【かつて使われた戸板】
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課
電話番号 0770-45-9111
メールフォームからのお問い合わせ




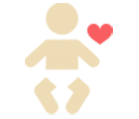
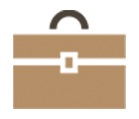
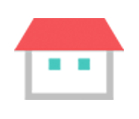
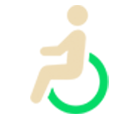
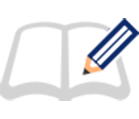
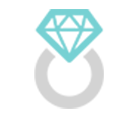

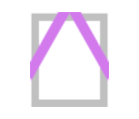



更新日:2022年03月31日