定額減税補足給付金(調整給付)について
【受付は終了しています】
申請期限 令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の確認書提出期限は10月31日(木曜日)(当日消印有効)です。
提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお急ぎください。
なお、期限を過ぎると給付金の支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
※対象となる方には、令和6年7月31日に支給確認書を送付しております。
制度概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、所得税・個人住民税の納付者及び同一世帯配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が実施されますが、減税前の税額から定額減税しきれないと見込まれる方には、差額を給付(調整給付)します。
※定額減税についての詳細は、下記をご覧ください。
【定額減税 特設サイト(国税庁HP)】(所得税)
【個人住民税の定額減税について】
個人住民税の定額減税について (PDFファイル: 220.5KB)
支給対象者
・令和6年度の個人住民税が若狭町で課税されている方
・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
※納税者本人の合計所得が、1,805万円を超える方、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)と令和6年度住民税所得割の両方が0円の方は対象外となります。
支給額
次の(ア)、(イ)の合計額を1万円単位で切り上げた額
所得税:定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=控除不足額(ア)
※定額減税可能額は、3万円×(本人+扶養親族の人数)
住民税:定額減税可能額ー令和6年度住民税所得割額=控除不足額(イ)
※定額減税可能額は、1万円×(本人+扶養親族の人数)
▼ここでの扶養親族には控除対象配偶者と16歳未満の扶養親族を含みます。(国外居住者を除きます)
算出方法の具体例
〈例1〉扶養がいない方で、所得税1万円、住民税所得割2万円(減税前)の場合
所得税:定額減税可能額3万円ー所得税額1万円=控除不足額2万円(A)
住民税:定額減税可能額1万円−住民税所得割額2万円<0=控除不足額0円(B)
⇒調整給付額は、(A)+(B)=2万円
〈例2〉扶養が3人いる方で、所得税3万円、住民税所得割額2万円(減税前)の場合
所得税:定額減税可能額3万円×4人ー所得税額3万円=控除不足額9万円(A)
住民税:定額減税可能額1万円×4人ー住民税所得割額2万円=控除不足額2万円(B)
⇒調整給付額は、(A)+(B)=11万円
※調整給付金は、所得税と個人住民税所得割のどちらか一方が課税で定額減税の対象であれば、税額0円の税目でも調整給付金が算出されます。
【具体例】扶養親族がいない方で所得税0円、個人住民税所得割額4,500円の場合
所得税:定額減税可能額3万円ー所得税額0円=控除不足額3万円(A)
住民税:定額減税可能額1万円−住民税所得割額4,500円=控除不足額5,500円(B)
⇒調整給付額=3万円(A)+5,500円(B)=35,500円⇒4万円(1万円未満切上げ)
申請方法
支給対象者には「確認書」を送付します。
確認書が届きましたら、記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し添付書類と一緒に同封の返信用封筒にてご返送ください。
※確認書は8月上旬から順次送付します。
確認書提出期限
令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効
(注)書類の不備等につきましても期限内に修正し、返送していただく必要があります。なお、期限内に返送されない場合、給付を辞退したものとみなし、給付金が支給されなくなりますのでご注意ください。
支給方法・支給時期
支給対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、9月以降順次振り込みます。
その他
本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」には十分ご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、若狭町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力せず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。




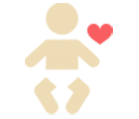
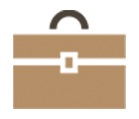
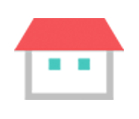
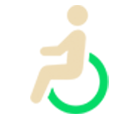
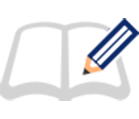
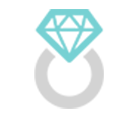

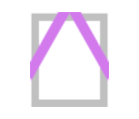



更新日:2024年10月21日