三方五湖

湖の歴史
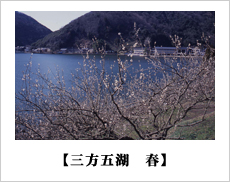
三方五湖には、三方湖、水月湖、菅湖、久々子湖、日向湖の5つの湖があります。
万葉集に「若狭なる三方の海の浜清みい往き還らひ見れど飽かぬかも」(作者不明 万葉集巻7)という季歌が残されています。三方五湖は、古(いにしえ)の時代から広く知られており、四季折々の美しさを持つ優雅な湖であったことがうかがい知れます。
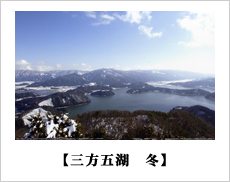
今から約2万年前の第4氷河期には、日本海の海面が100メートル以上も下がり、三方五湖は海岸から遠く離れた内陸の湖でした。そして、約5千年前の縄文時代前期には、海面が現在より3~5メートルも高くなり、三方湖は現在の約2倍の面積がありました。その後、海面が下がり、ほぼ三方五湖の輪郭ができた頃、久々子湖はまだ大きな入江でしたが、耳川によって海に運ばれた砂が入江に堆積し、入口がほとんどふさがれてしまったことで久々子湖(潟)が誕生しました。このように形成された久々子湖は潟湖であり、他の湖は三方断層の沈降部にできた断層湖とみられています。
最南部の三方湖は、元々西北の水路で水月湖と通じていましたが、水月湖と久々子湖の間は、寛文2年(1662)から開削された浦見川によって結ばれました。さらに、宝暦1年(1751)の嵯峨隧道(ずいどう)開通により水月湖と日向湖がつながりました。こうした人工的な開削により五湖が連結され、現在のような三方五湖の形になりました。
湖の自然・水

三方五湖は、若狭湾国定公園に位置する代表的な景勝地で、湖周辺と北西に伸びる常神半島を含めた地域は、昭和12年(1937)6月15日に名勝「三方五湖」として国の指定を受けています。三方五湖周辺のなだらかな湖岸の風景は、リアス式海岸である若狭湾の切り立った日本海の風景とは対照的な風情があります。
こうした三方五湖の大きさと海水の特質は、次のようになっています。
- 三方湖
(最大水深3.4メートル、面積3.58平方キロメートル)
五湖の内ただ一つの完全淡水湖で、コイ、フナ、エビ、ウナギなどが捕れます。 - 水月湖
(最大水深33.7メートル、面積4.18平方キロメートル)
海水と真水が半々の汽水湖で、魚は湖の中層より上に生息しています。低い丘陵や、湖畔沿いの梅林などに囲まれ、緑豊かで穏やかな風情に満ちています。 - 菅湖
(最大水深13.7メートル、面積0.91平方キロメートル)
水月湖と同じ汽水湖で、湖辺一帯は鳥類の禁猟区になっています。 - 久々子湖(最大水深2.3メートル、面積1.40平方キロメートル)
汽水湖ですが、満潮時には日本海から海水が逆流し塩水にもなります。海と繋がっている湖だけに、海の魚が豊富な湖で、スズキ・ボラ・シジミなどが生息しています。 - 日向湖
(最大水深39.4メートル、面積0.93平方キロメートル)
完全な塩水湖で、魚類はタコ、クロダイ、ボラ、イワシなどが捕れます。
湖と景観

三方五湖の景観の特色は、低いゆるやかな丘陵性の山々を湖の周囲に巡らし、温和で素朴な情緒があふれています。車で「レインボーライン」を通って、標高約400メートルの梅丈岳(ばいじょうだけ)山頂に登ると三方五湖が一望できます。5つの湖は水質や水深が違い、すべて濃さの違う青色に見えることから「五色の湖」と呼ばれています。
三方湖、水月湖は、色鮮やかな新緑や紅葉を湖畔の水面に映し出します。自然と調和している家並みや湖を囲む低い丘陵、湖畔沿いの梅林など、緑豊かで穏やかな風情に満ちています。
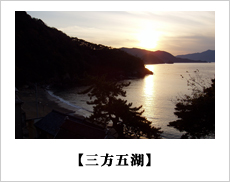
変化に富んだ地形と緑あふれる若狭町の自然は、鳥類にとっても非常に棲みやすく毎年渡り鳥がたくさん飛来します。特に、菅湖とその周辺全域は「特別鳥獣保護地区」に指定されており、オジロワシ、オオワシ、カモ類などを観察することができます。
隣町の美浜町にまたがる久々子湖は、単調な砂浜と松林の続く久々子海岸、松原海岸に接している美しい景勝地で、北端の岳山から日本海と三方五湖を眺めることができます。
日向湖は、周囲に急峻な山をめぐらし、あたかもすり鉢の底に水をたたえたような形で、日向湖北岸には、山と湖にはさまれた狭い湖岸の山陰に、細く長い日向集落が軒を連ね、漁村風景の趣が感じられます。
湖とともに

三方湖、水月湖、久々子湖周辺では、水田などの農地や民家、公共施設などが浸水した経験があるため、昭和51年(1976)から湖辺災害復旧工事を行い、護岸を今までよりも1メートルほど高くしました。しかしここ数十年、三方湖の護岸工事の進展とともに湖辺のヨシやヒシなどの水生植物が極端に少なくなってきたことや、合成洗剤や化学肥料の含まれた生活雑排水、農薬の含まれた農業排水などが湖に流入したことで、湖水の汚濁が急速に進み、湖が富栄養化しアオコも多く発生しました。

こうした水質悪化に対し、集落の下水道を整備し生活雑排水が湖へ流入することを防ぎ、ヨシの浮き礁を設置し湖の富栄養化を減少させることに取り組んできました。各家庭では、粉せっけんを使用し、米のとぎ汁発酵液を川に流さないようにすることで、生活雑排水が湖に流入することを減少させ、湖に環境負荷のかからないように努めています。
ボランティアや各種団体、学校などでも、町の大切な宝である湖をきれいに守るために、湖周辺のごみや空き缶拾い、環境学習などを通して環境美化活動を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課
電話番号 0770-45-9111
メールフォームからのお問い合わせ




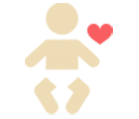
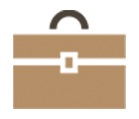
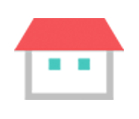
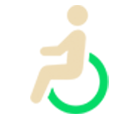
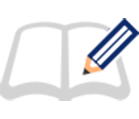
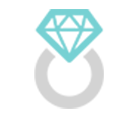

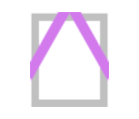



更新日:2022年03月31日